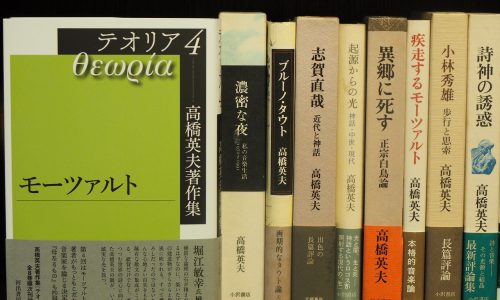八月十六日の夜、京都に降っていた雨はほぼ止み、無事五山に送り火の火が点りました。今年はテレビの中継を通じて拝見しましたが、京都盆地を囲む五山に設けられた火床に次々と火が入り、夜空に炎の文字や形が浮かび上がる光景は何度見ても心に沁み入ります。五山送り火は本来は都人たちの祖霊送りですが、万人がそこに心を寄せたくなる力があるように感じます。
五山送り火の前夜、京都の松ヶ崎で題目踊りとさし踊りが行われました。京都の松ヶ崎は五山のうち妙法を守っている地域で、これらの踊りは送り火と共にお盆の行事として長く受け継がれています。洛北に伝わる最も古い形の盆踊りで、江戸時代には後水尾天皇がご覧になったとも伝わるこれらの踊りは、檀家で組織する松ヶ崎立正会によって守られており、京都市の民俗無形文化財に指定されています。踊りが行われるのは送り火の「法」が点される東山に近い湧泉寺です。
(写真はphoto AC)
松ヶ崎が位置するのは京都盆地の北、高野川と賀茂川に挟まれたところで、東に比叡山を望むことができます。背後の虎の背山(妙の字が点る西山から法の字が点る東山まで連なる低山)に松が茂っていたので松ヶ崎と呼ばれるようになったとのことで、平安遷都に際し平城京の百姓百軒を移住させ宮中に納める米作りをさせたことに始まるとも言われます。湧泉寺はそうした松ヶ崎の中心にあります。現在は日蓮宗ですが、元は平安時代に建立された比叡山三千坊の一つ天台宗の円明寺(後に歓喜寺と改称)というお寺でした。鎌倉時代の徳治元年(一三〇六)に住職の実眼が日蓮の孫弟子にあたる日像上人に出会って心服し、お寺を日蓮宗に改宗、妙泉寺としますが、村人たちからは改宗を拒まれます。そこで日像上人を松ヶ崎に招いて説法をしてもらったところ、村人たちは全員日蓮宗に改宗することになり、喜んだ実眼が題目を唱えると村人たちが踊りながらそれに和したとのことで、それが題目踊りの始まりと伝わります。(戦国時代に流行した念仏踊りを模倣したという説もあります。)妙泉寺は後に本湧寺と一つになり、現在の湧泉寺となりました。
松ヶ崎で村をあげて日蓮宗に改宗したことを記念し、日像上人が虎の背山の西にある西山に妙の字を描き、さらに後の江戸時代には下鴨大妙寺の日良上人が東山に法の字を描いたと伝わります。そこに村人たちが字の周りに杭を打ち松明を置いて炎による文字を描いた、それが妙法の送り火の起源のようです。妙法は言うまでもなく日蓮宗のお題目「南無妙法蓮華経」に由来します。ちなみに五山送り火自体がいつから現在のような形で行われるようになったのか、確かなことはわかりませんが、江戸時代の日記から江戸中期には存在していたと考えられ、松ヶ崎でも初期から妙法の二文字を送り火の際に点していたようです。
余談ですが、妙の字は草書体、法の字は隷書体と字体が異なり、同時に描かれたものではないということがうかがえます。
例年題目踊りとさし踊りは八月十五日と十六日の夜に行われますが、今年は十五日のみでした。夜八時からの踊りに間に合うよう少し早めに松ヶ崎に着き、のんびりお寺に向かって歩いていると、山の南側斜面に翌日の点火を控えた「法」が見えました。現在の火床はステンレス製の受け皿に割木を乗せてあります。妙は町ごと、法は家ごとに点火する火床が決まっているそうです。
踊りに先立ち十五日の昼間湧泉寺本堂でお盆の施餓鬼会が行われていますが、お寺に到着したときは人の姿がなく、初めて来る場所で少し不安になりましたが、あたりが薄暗くなる頃、ぽつりぽつりと浴衣姿の人たちが集まりはじめ、提灯に灯が入るとようやく踊りの会場らしくなっていきました。
八時が近づき関係者もほぼ揃ったようで、しばらくすると堂内で読経が始まりました。
十数分ほどで読経は終わり、皆さん本堂から出てくるとそれぞれの持ち場につきます。歌い手たちは本堂に向かって右に男性、左に女性と分かれて立ちます。
「では題目踊りを始めます」という男性の合図で、太鼓が鳴り、静かに踊りの輪が動き出しました。
盆通りというと、賑やかに踊る様子を思い浮かべますが、松ヶ崎の踊りは動きも少なく地味です。両手を腰にやり、ゆっくりと数歩進むと、輪の中心に向きを変え膝を曲げ、伸び上がったところでまた前にゆっくりと進む、これをしずしずと繰り返します。この所作は稲が実り穂を垂れる様子を表しているそうです。
歌は男女で掛け合うように歌われますが、法華経を称える内容のためか声明のように聞こえてきます。太鼓の音も、歌の要所要所を締めるように、トントンと静かにたたかれます。
踊りは曲によって扇を手にするなど所作が異なりますが、どれも体の動きは少なく、粛々と進行していきます。檀家の人たちだけで踊られる松ヶ崎の宗教行事としての踊りは、昨今のイベント化している盆踊りとは一線を画すもので、中世に時間を巻き戻したような幻想的ともいえる情景に見入りました。
半時間ほどで題目踊りが終わると休憩を挟み、今度はさし踊りが行われます。さし踊りは洛北に伝わる鉄扇や紅葉音頭と同じ系統で、楽器を用いず音頭取りの音頭に合わせ、櫓の周りを輪になって踊る盆踊りです。
中央に櫓が置かれ、音頭取りたちが狭い台に上がると、踊りが始まります。さし踊りは関係者以外にも開かれたもので、見学者たちも是非一緒にと声をかけられましたが、踊りは単純そうでいて細かな所作がすぐには覚えられません。さし踊りの「さし」は差し上げるとか捧げるという意味ですから、奉納踊りということなのでしょう。しばらく輪の外から見ていましたが、手の動きが優雅ではんなりと京都らしい踊りでした。
中世に起源を持つこうした踊りは洛北の他の地域、たとえば上賀茂や修学院などにも残っています。つくづく京都というのは奥が深い土地だなと。
松ヶ崎の題目踊りとさし踊りは中世の踊りの名残を伝えるもので、先祖供養という盆踊りの本来の意味を感じさせてくれるものでした。